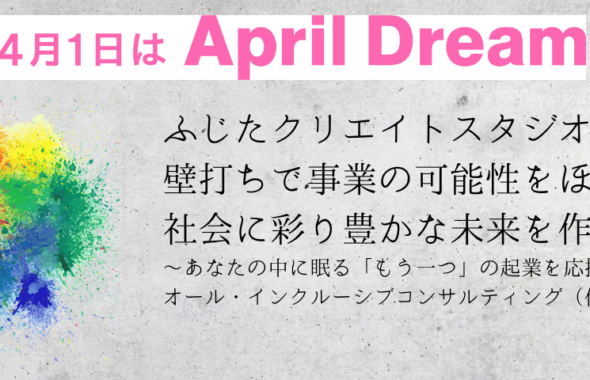【当事務所についてその17】当事務所の思う「信頼」のこと
VUCA/VANI時代の新しい事業や創業を「壁打ち」で伴奏する触媒・外部デバイスでありたい、中小企業診断士、国家資格キャリアコンサルタントの藤田有貴子です。
このシリーズでは当事務所について書いてまいりました。バックナンバーはこちらです。
その1「当事務所の名前の由来」、その2「中小企業診断士とは」、その3「フリーランスとは」、その4「藤田有貴子ってどんな人間ベース編」、その5「国家資格キャリアコンサルタントとは」、その6「カオスの時代にクリエイトしていきます」、その7「カオスについてどう向かっていくか」、その8「アートとサイエンス問題」、その9「断捨離が必要」、その10「営利非営利のカオス」、その11「ほぐすのが得意かもしれません」、その12「ほぐしているとみつかる気がするんです」、その13「社交的ではない代表でも、人は好きなんです」、その14「初めてのみなさまへご挨拶」、その15「登録しております日本最大級の起業支援プラットフォームDreamGateのこと」、その16「【当事務所についてその16】当事務所の名前についている「クリエイト」のこと」
本日は「信頼」について語ってみようと思います。
1:信頼とは
Wikipediaによると「信頼(しんらい)とは、相手や対象に対し自分の期待した通りの結果が帰ってくることが信じられること。どれだけ信じられるかの定量的度合いを信頼性や信頼度という。」とあります。
期待が返ってくるか?信じられるか?ということのようですね。
「信じる (しんじる)」とは、Wikisionaryによると、①(他動詞)正しいと考える。うそ偽り無く確かに正しいまことの事だと強く思い込んで受け入れる。②(他動詞) 当てにするに足りる頼もしい相手であると見込んで心を寄せる。信を置く。信用する。信頼する。(以下略)のようです。
「信じる=心を寄せるべき人かどうか」ということですね。
Perplexityさまの回答(こちら)
信頼とは、相手の将来的な行動や感情に対して期待を寄せることです12。これは単なる過去の実績評価である「信用」とは異なり、より主観的で感情的な要素を含みます12。信頼関係は、お互いが安心して頼り合える状態を指し、心理学では「ラポール」とも呼ばれます2。
この関係性は、以下の特徴を持ちます:
信頼を構築するには、責任ある言動と誠実な対応が重要です1。約束を守り続けることで、相手に安心感を与え、信頼関係を築くことができます1。ただし、信頼の定義は個人によって異なる場合があります3。自分にとっての「信頼」の意味を理解することで、より良い人間関係やビジネス関係を築くことができるでしょう。
ーーー
と、パープレさん今回も数分で算出。すごいですよね。
もうちょっと…「信頼経済」についてもきいてみました。(こちら)
「信頼経済」とは、「社会や経済システムの基盤として信頼が重要な役割を果たす経済モデル」です。この概念は、経済活動や社会の発展において信頼が不可欠であることを強調しています12.
信頼経済の特徴
- 取引コストの削減: 信頼が高い社会では、監視や契約の執行にかかるコストが低減され、経済活動が円滑になります1.
- 協力関係の促進: 信頼は職場や取引先との協力関係を築く上で重要な要素です1.
- 制度・システムへの信頼: 個人間の信頼だけでなく、社会制度やシステムへの信頼も経済活動を支えています1.
- 貨幣システムの基盤: 通貨の価値と機能は、社会全体の信頼に基づいています1.
信頼経済の影響
- 経済発展: 信頼度の高い社会ほど経済発展が進むことが示されています1.
- 社会的複雑性の縮減: 信頼は社会システムを簡素化し、効率を高めます1.
- 資源の有効活用: 信頼によって節約されたコストを教育や福祉などに投資できます1.
信頼経済の考え方は、従来の競争中心の経済モデルとは異なり、協力と信頼関係を重視します5. この概念は、経済活動だけでなく、社会全体の繁栄と安定にも寄与する可能性があります。
ーーー
さすがです!ありがとうございました。
まとめると、「信頼」の定義は個人によって違うけれど、「信頼」は「過去と今後も含めて相手を信じられる、期待をできること」、その信頼を築くには「責任ある言動と誠実な対応、約束を守ることが大事」のようです。
そして「信頼」は「信頼経済」として協力と信頼で取引コスト(審査したり、信頼構築への手間がかかる意味)を減らしてしっかりお付き合いをしていく世界もできているということのようです。
ただ、これが善だけともいえず、個人によって信頼の定義は違うので、思い違いがあったり、信頼できないものが突如入りこんでくる可能性もあり、対策もいるのではと思うところです。
2:信頼って「〇し」と「〇〇〇〇」の元?
信頼や信頼経済の定義をみて、感じたのがこれらのワードです。
「信頼は過去及び今後も含めて相手を信じられる、期待をできる対象」って「推し」という存在を指すのではないでしょうか。誰にも強いられることなく、純粋に推しを応援する、推しを見に行く、推しに励まされる、それは信頼があるからだと思います。一方、推しが思う存在ではなかったとか、スキャンダルがあるとがっかりしますね。まさに推しとの信頼関係。
推し活総研の大規模アンケートでの調査によると、2024年推し消費の市場規模は約3兆5千億円に達するそうです。大きいですね!
「信頼を築くには責任ある言動と誠実な対応、約束を守ることが大事」というのは「ブランド」に近いように思います。ブランドの起源は焼き印といわれています。うちのブランドの焼き印を押すことは、製品商品サービスに信頼をつけたということです。焼き印を押したブランドを誠実な対応で約束を守ってきたから、ブランドがブランドとして認められているのだと思います。ブランドが偽物だったり、対応がよくなかったり、世界観とずれていたり、そのブランドを身に着けている方はふさわしくないとブランドの価値が棄損される(下がる)ますよね。
ブランドの価値というのは、個人が持っている「ブランドアイデンティティ(気持ちの合計)」、のれんとして会計上になる「ブランドエクイティ(財産)」の両面があります。これらの価値はブランドが時間をかけた信頼そのものなのではないでしょうか。
これからの時代は「信頼」が大事になると多くの方がおっしゃっていますし、私もそう思います。理由は①VUCA・VANIといわれる不確実で変動性が高くてあいまいで…と何が正解かわからないので、信頼が評価基準になるということ、②一時的ではなく長い目でみると信頼が高いものが一番良かったになること(ブランドものというのはその意味もあるのでしょう。それだけではありませんが)、③信頼でつながるコミュニティやつながりはなにか心地いいし、代えがたい幸せがある(お気に入りのお店はそうですよね)、ということでしょうか。
3:私が考えている「信頼」とは
以下のように思っています。
1:正直でいる、フェアでいること
これはもう価値観なのですが、ご縁があって出会った目の前の方に私のリーチする無限の可能性から最もいい選択肢を選んでほしいと思っています、心から。「どの人にとってもいい商品サービス」は絶対にない!って思っています。一緒に探索しつつ、選んでいく、創っていく過程が私の喜びです。なので壁打ちが好きなのです。
壁打ちもやり方にこだわりません。能力に限界はありますが、私なりに相手によって無数のアプローチから直感も含め、自由なその人に合ったものを選びたいと思っています。
そして両者の関係で、自分が相手の利に取られている気がする関係は整理するようにしたらすっきりしました。先方も本能的で意図してはないからこそ、「お!バランスおかしい!」と気づいたら、自分も選んでいいって思っています。
ネガティブなことばを伝えられ続ける関係も避けました。ひととひととの相性は絶対あるのですが、相性やテイストが合わないことを言語化してブロードキャストされるのは違うかなと思っています。なのでそういうのも苦手です( ;∀;)
脱線しましたが、これはあくまでも私の好み。みんな違ってみんないいんだと思います。
2:約束は守る、守れないときはちゃんと言う
「約束を守る」は信頼の基礎だといわれています。商談や融資や金融機関で約束を守れないことは会社として存続できないことを意味します。そこまではなくても、社交辞令は同調圧力とかプロトコルで決まっている(それを決行すると場によくない)以外はできるだけしないようにしています。「会えないのに会いましょう」「いけないのにいきます」とかは言わないようにしています。せめて「行けたら行きます」というようにします。
自分も本当に約束を守れる人、YESNOのお返事が言える人とちゃんとかかわりたいと思うからです。断るときは理由そのものに支障があるとか、プロトコル以外では言える範囲で理由も言うようにしています。
もちろん諸所の事情で言えないときもありますが、それはもう信頼が切れても仕方ないと考えることにしています。
3:一貫性を持つ
自分なりに「手段にとらわれず多くの可能性を大事にする」という価値観、一貫性を持ってきました。「異端児をハッピーに」というユニークさを大事にする価値観や発想は変えていません。私の生きる根源だからです。言語化は難しいのだけど、いろいろな言葉で発信しています。
もちろんひとそれぞれで相性があるので、全員と信頼関係を築くのは難しいです。
フリーランスであるため、所属するところかかわるところはレスペクトしますが、一定のコミュニティや会社、団体と大きく信頼を築くのではなく、フラットに独立してかかわるようにしています。そこの所属でなくても自分の信頼は変わらないですし、このスタンスが理解しあえる築きたい人と築いていきたいと考えています。相手に自分のコミュニティに入ってほしいというのではなくて、相手が別のコミュニティを選ぶことにwelcomeといえて応援できる自分でいたいんです。SNSで人とタグをつけないのもその方針があるからです。
フリーランスになるとその一貫性は強化され、蓄積されているように思います。あわない仕事はだめになりますが…あう仕事、あう仕事仲間は磁石のように引き付けられ増えている気がします。
一貫性を持つほうがいい人と変な色を持たないほうがいい人がいるかもしれませんが、私は年を取っていくと蓄積されてくるこの生き方でよかったです。現代はこのほうがあってきた気もします。
最近質問とかで今の時代では「あれ?」ということをいうことがあります。でもいいんです。10年後に「あの時あんなこと言ってた」と思っていただければいいなと、そんな存在であり続けることが、私の「信頼」です。
みなさまにとっての「信頼」はどういうものでしょうか。機会があればお話しできると嬉しいです。
当事務所でも毎月11日(原則)開催の「夢を進める壁打ちラウンジ(2025年1月に夢をかなえるか壁打ちラウンジより改名)」を開催しています。スケジュールはこちら(DreamGateのホームページ)です。ご質問やご相談は、お問い合わせフォームよりお尋ねください。
お互いによい形で進みますように!最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。