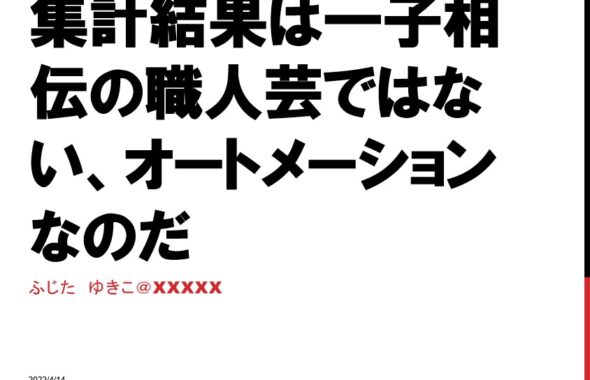【当事務所についてその8】ドラマ「ブラックペアン」をみて思ったサイエンスとアート問題
前回、その1(当事務所の名前の由来)、その2(中小企業診断士とは)、その3(フリーランスとは)、その4(藤田有貴子ってどんな人間ベース編)、その5(国家資格キャリアコンサルタントとは)、その6(カオスの時代にクリエイトしていきます)、その7(カオスにちうてどう向かっていくか)ついて書いてまいりました。
今回も引き続きドラマ「ブラックペアン」を見て気づいたことついて書いていきます。
Q1:ブラックペアンとはどんなドラマですか?
回答:
TBS系日曜劇場で2024/7/7(日)21時から放映しているドラマです。正式名称は「ブラックペアンシーズン2」のようです。2018年4月~6月まで、同日曜劇場にてテレビドラマ化された1は見ていませんので、表層的なことはわかりません。なお、原作は『ブラックペアン1988』は2007年に講談社から発売された海堂尊の長編小説で、天才外科医のお話です。wikipedia
Q2:なんで気になったのですか?
詳細:
公式サイトでは「手術ではない、これは芸術だ」と書かれていますが、ブラックペアンは天才心臓外科医が世界で誰もできない難しい手術を芸術的に行い、患者様を治すというストーリーです。私の母も難しい手術を経験したので、その時の先生は神様のように感じます。母の執刀医は人格者でいらっしゃいましたが、主人公の先生はそうではないようです(ドラマだと)。
マーケティングのゼミで「マーケティングはサイエンスかアートか」という議論を学びました。これというページはないのですが、検索エンジンで検索されると記事が出てきます。マーケティング施策というと広告施策がメジャーですが、すごくセンスのいいCMやクリエイティブは売上につながります。これは考えつくされたサイエンスとも違うように思います。ネットでの集客は結構データサイエンスです。
医療における手術というとテクノロジーの塊のように思いますが、関係者のお話を聞いていると手技の様な手の器用さやセンスが問われるというようにも聞きます。
Q3:お仕事はテクノロジーかアートなのか
回答:
私たちのお仕事、コンサルティングや伴走型(伴奏型)支援についてもそうかなとおもいます。行動経済学では、人間には早い思考(ぱぱっと判断)と遅い思考(じっくり考える)があるといわれています。遅い思考でトレーニングをすると早い思考でぱぱっとできるようになります。これは自転車や自動車の運転も、語学もそうでしょうし、熟練の技は修行をして遅い思考が早くなることです。
創業セミナーで「ぱぱっとできることや人にすごいといわれることから事業を考えてみましょう」というお話をします。そこは個々人が生まれ持つセンスなのだとおもいます。スポーツや音楽などルールがあるものですごい人はいますが、私たちにもきっと何かの定義では優れていることがあるような気がします。ブラックペアンであれば、心臓縫合技術がものすごい得意ということもあるかもしれません。
この話で思い出すのは「にぎりびと」という方のことです。(東洋経済オンラインの記事)その方が炊飯器で炊き立てのご飯でおにぎりを握ると、みんながそのおいしさに感動するそうです。お呼びがかかり、国内や海外にもいかれることもあるとか。この方がおにぎりやさんを出していたら、もちろんおいしかったでしょうけど、唯一無二の存在になったでしょうか?定食屋さんだったらおにぎり以外にも様々な要素がありますので、ここまでの魅力は際立ちにくかった、知られるのに時間がかかったかもしれません。なので、これからの世の中は得意なセンスを入れた能力とどう切り出すかが大事なのかなのではと思います。
お互いみつけてみませんか?
なお、2024/7/11(木)21時、夢を叶える壁打ちラウンジ空いてますよ♪(アピール)今週は割と忙しく、いらっしゃらなければそれはそれと思っていますが、気になる方いらしてください。
最後まで長文におつきあいいただき、ありがとうございました。