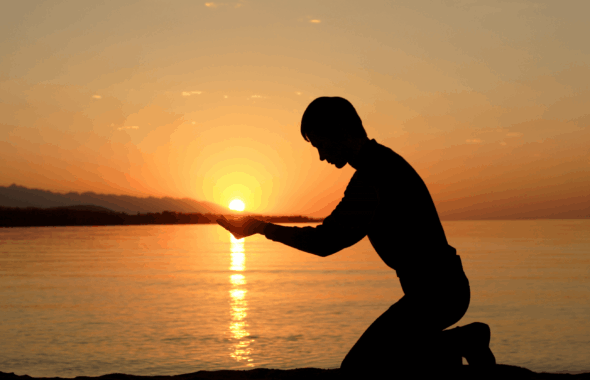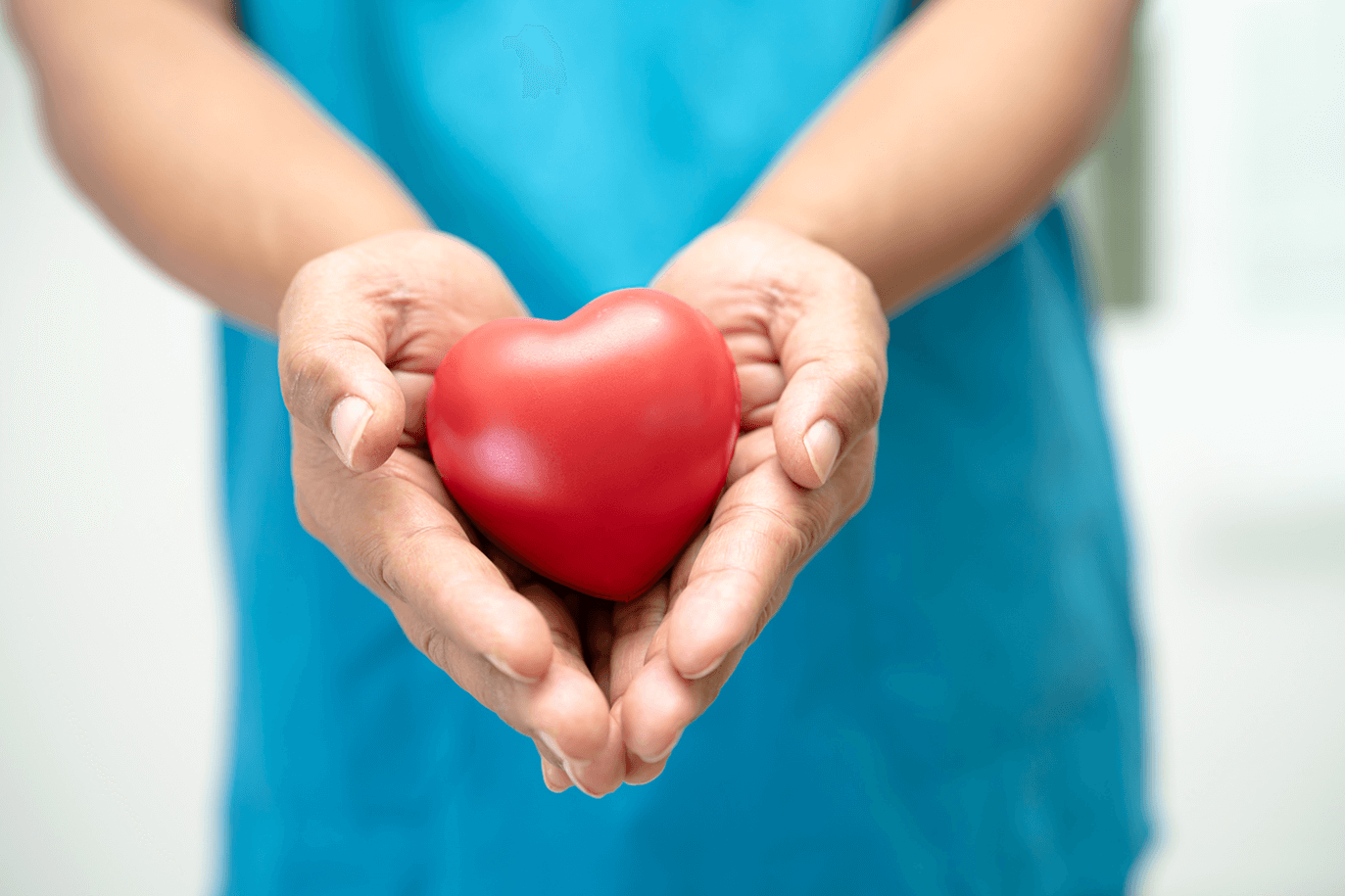
【VUCA/VANI時代の新しいキャリアを思うその9】giverとしてどう生きていくか
VUCA/VANI時代の新しい事業や創業を伴奏する触媒・外部デバイスでありたい、中小企業診断士、国家資格キャリアコンサルタントの藤田有貴子です。
キャリアコンサルタントして「転職7回でフリーランスになったキャリア」として綴らせていただいているシリーズ
その1学生と新卒での就職について/その2社会人初期について/その3国家資格を取ることについて/その4独立自立マインドが強いかもしれないひとの生きる道/その5いろいろな方に会ってみる、その6標準パッケージとオリジナルパッケージの話/その7デジタル、バーチャルの時代のビジネスにおける価値/その8うろうろすることの意味
今回は、先日ある方に「天然のgiverですよね」といわれたことがあり、giverについて生成AIから引用しつつ、深めてみようと思います。
Q:ギバー(giver)とは
A:ChatGPTさんにお聞きしてみました。
ーーー(引用はじめ)ーーーー
「ギバー(Giver)」とは、他者を中心に考え、相手が何を求めているかを注意深く考えるタイプの人を指します。 彼らは与えることに対して見返りを期待せず、手を差し伸べる、いわば「奉仕する人」です。心理学ワークショップ+4スポーツナビ+4note(ノート)+4
この概念は、アダム・グラント氏の著書『GIVE & TAKE(ギブ・アンド・テイク)』で提唱されたもので、同書では人間の行動パターンを「ギバー」「テイカー」「マッチャー」の3つに分類しています。 「ギバー」は他者に惜しみなく与える人、「テイカー」は常に多くを受け取ろうとする人、「マッチャー」は与えることと受け取ることのバランスを考える人と定義されています。スポーツナビ+7note(ノート)+7Foresight+7スポーツナビ+2仕事探し | Indeed (インディード)+2note(ノート)+2
また、ギバーには2つのタイプが存在します。一つは「自己犠牲型」で、他者の利益には関心があるが、自分の利益には無頓着で、人に与える一方で自分の利益を損なってしまうタイプです。もう一つは「他者思考型」で、他者の利益と自己の利益の双方に関心があり、受け取るより多く与えるが、自分にも他者から還元されるように行動するタイプです。 Foresight+3スポーツナビ+3仕事探し | Indeed (インディード)+3
このように、ギバーの行動は他者への配慮と自己利益のバランスによって異なり、成功や幸福感にも影響を与えるとされています。
ーーー(引用終わり)ーーーー
Giverは「自己犠牲型」と「他者思考型」があるということで。「自己犠牲型」は疲れてしまう(私も過去何度も疲れています…)ので、他者の利益と自己の利益の双方に関心があり、受け取るより多く与えるが、自分にも他者から還元されるように行動するタイプである「他者思考型」について深めていこうと思います。
Q2:「他者思考型giver」はなぜ幸福感が高いか?
A:こちらについてもChatGPTPROさんにご相談させていただきました(ありがとうございます)。
ーーー(引用はじめ)ーーーー
「ギバー(Giver)」とは、他者に惜しみなく与える人を指し、アダム・グラント氏の著書『GIVE & TAKE(ギブ・アンド・テイク)』で提唱された概念です。
ギバーが幸福感を得る理論的背景として、ポジティブ心理学の「PERMAモデル」が挙げられます。このモデルは、幸福感を構成する5つの要素を示しています。 positivepsych.jp+2Musubuライブラリ | BtoBをハックする BtoB大百科+2sparkle-wellbeing.com+2
- Positive Emotion(ポジティブ感情): 愛や感謝、喜びなどの肯定的な感情。Musubuライブラリ | BtoBをハックする BtoB大百科
- Engagement(没頭): 時間を忘れるほど何かに夢中になる状態。Musubuライブラリ | BtoBをハックする BtoB大百科
- Relationship(良好な人間関係): 他者との良好な関係性。
- Meaning(人生の意味): 自分より大きな何かに貢献することで得られる意義。dakaboku.jp
- Accomplishment(達成感): 目標を達成した際の満足感。
ギバーは、他者への貢献を通じて「Relationship」や「Meaning」を深め、結果として「Positive Emotion」や「Accomplishment」を得ることができます。これにより、持続的な幸福感(ウェルビーイング)が向上するとされています。sparkle-wellbeing.com+1Musubuライブラリ | BtoBをハックする BtoB大百科+1
また、ギバーの中でも「他者志向タイプ」の人は、相手の利益を考えつつも自分の利益も見失わないため、自己犠牲に陥らず、幸福感を維持しやすいと指摘されています。 yoi
さらに、ポジティブな思考を持つことは、長生きや生涯年収の向上など、豊かな人生につながるとされています。 Schoo
これらの理論から、ギバーの行動は幸福感の向上に寄与すると考えられています。
ーーー(引用終わり)ーーーー
「他者思考型giver」になると、いいことばかりですね^^
あと、ここで大事なことは「器」「ステージ」ということだと思います。「虫の目、鳥の目、魚の目でみましょう」※という言葉がありますが、器がある、つまり様々な視点を使い分けることで多くの気づきが得られる気がします。「他者思考型giver」の最終系は「器の大きな人だ」と思ったりしました。
※「虫の目、鳥の目、魚の目」とは、物事を多面的に捉えるための視点の例え。虫の目(ミクロの視点)細部を注意深く観察し、現場や具体的な事象を深掘りする視点、鳥の目(マクロの視点)上空から俯瞰するように、全体像や広い視野で状況を把握する視点。魚の目(トレンドの視点)時間の流れや変化、トレンドを捉え、時代の流れを見極める視点。
Q3:「他者思考型giver」としてどう生きていくか
1:他者の利益とは
「相手の喜び」や「相手が得をすること」ということですね。それが短期的なところだったり、長期的なところだったり、どういう立場だったり、視点があるような気がします。
私は、酒席で前に座っている相手のビールが空いているところが全く分からないんです。それだけを気にしようとすると会話できない(;’∀’)酒席で言うと「とりあえずビール」でビール以外を頼んではいけない空気もどうも苦手です。特に「女性がすべき」というところがあるとしんどかったです。でも今はそういう空気感は減っていていい時代です。
一方、相手の話を聞いてふわっと何が必要かとらえるのは比較的得意かもしれません。ビジネスをされたい方のお話をお聞きしていると、事業計画やビジネスモデルなどのイメージがつながっていて、直感で身体でストーリーが始まり育っていきます。
ここでいえるのは相手の喜びを感じ取れるポイントは各自のギフト(個性)ではないかということで、その部分を強めていけばいいのではと思います。フリーランスになって得意分野に寄せて、苦手なことはできるだけ得意な人にふりますし、逃げます。
もちろん「これといって得意なことはないんです」というかたはおそらく総合型だったり、まだ明らかになっていない個性があるということで、今あることを自分ができる範囲で貢献したり、手伝ったり、気づいたことを言ったりして、それぞれ他者の利益を考えればいいと思います。
「どうしても無理なんです」であればその場があっていないかもしれません。ビギナーであれば、だれかがサポートしてくれるシステムがあるはずです。なければ、誰かに相談をしてその方法でトライしてみたうえで、難しければ変えるということに許容度が高まっています。一方持ちこたえることでついた力は経験の力でまねされにくい独自のものです。それも選択です。
相談する相手は、上司や先輩、価値観をわかってくれる第三者の理解者(ここ大事、社外であることもあるかも)、心理系のカウンセラーさんなど心理的医療的な視点でもあってもいいとおもっています。ただここで違う方向に引っ張る方もいるので、複数名聞くようにしています。選択肢のひとりとして生成AIもおすすめです。
ここで言いたかったのは「自分なりに他者の利益や他社の意思の尊重を考えるならOKではないか」ということです。その自由度が個性になるように思います。
2:自己の利益とは
私自身もGiver(ギバー)というと、自己犠牲型という自分がすり減ってしまうイメージを持っていました。年を重ねると、経験値が上がり、耐性ができてきた気がします。
どんな相手と自分でも何かの資源が行き来します。それが自分にとって利益となる資源とは「お金」と「時間」と「感情」などに分けられ、それがマイナスになっている状態が続いてしまうというのが自己犠牲だと思っています。
お金:相手が不当に働かせようとしていないか、お金をとってこないか
時間:相手が自分に対し、自分への報酬がないのに一方的に時間を要求してこないか
感情:相手が自分に対し、嫌がらせをしていないか。自分と人で態度を変えていないか
ここで相手にはだます意図はなく、魅力的ないい人であるという例があります。相手は相手でがんばっています。これをチョイスするのは自分自身の決断です。この線引きを決めると楽になりました。幸い、会社の従業員であればハラスメントは大きな問題として解決もされつつあります。フリーランス法として一部守られてきていて、いい時代になっています。
なお、お金も時間も投じたいのが「推し」ということでしょう。
ただこの辺りは「お互いにどう思うか」も大きいので完全にはなくならないと思います。
これについては、
1:「肉体の限界を理解する」 疲れていると気づきにくいです。身体は大事です。後で振り返ると別の気づきがあったり会います。
2:「自分がやりたくてやっているか」主導権は自分にあるかを考えることも大事です。人生生きていると「めんどくさいのでつきあう」「あえてゆだねて楽しむ」というケースもありますが、それもあくまでも主導権は自分にあります。それが難しければ手放すのもありかと思います。
3:「自分が何が欲しいかを明確にする」 これがほしいならこれは許容するというようにメリットデメリットでロジックを入れて、納得をすることもできます(無理に納得するということではなく、心から納得するのを数値とか見えやすい指標で助けるという意味です)。ただ私もそうですが、欲しいとか、わからないなど判別がついていない分野もあるので、それについてはほかの大事だったりすることや直感に頼るか相談するかなのかもしれません。
あげてみましたが、いかがでしょうか。みなさまにとって何かヒットするものがあると嬉しいです。
お知らせです
①夢を叶える壁打ちワークショップ 2025/3/21(金)7:00-と21:30-開催
朝(早朝7:00~8:40)[PG010]夢をかなえる壁打ちワークショップ(朝編)
公式サイトはこちら、事前申し込みのpeatixはこちら
夜(深夜21:30~22:50)[PG009]夢をかなえる壁打ちワークショップ(夜編)
公式サイトはこちら、事前申し込みのpeatixはこちら
②夢を進める壁打ちラウンジ(1対1)
ご質問やご相談やお仕事として依頼したいなどは、お問い合わせフォームよりお尋ねいただけましたら、別日程でも相談をお受けいたします。